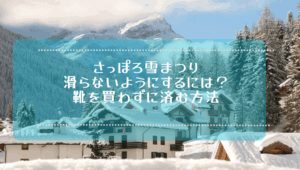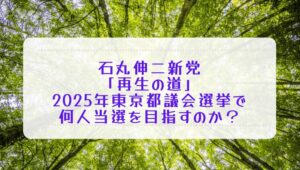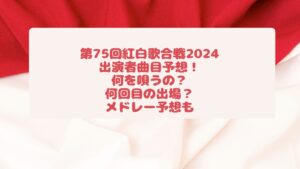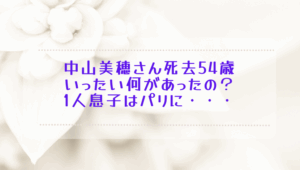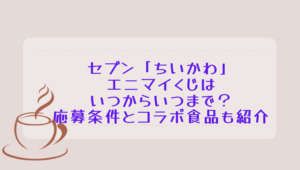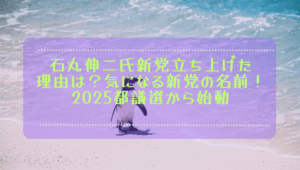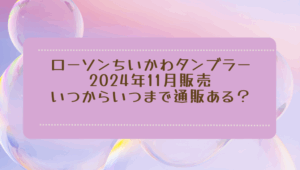女性管理職は、チームを纏め部下がいます。またチーム内の予算、目標管理など責任を負います。会社によって役職のつけ方、また権限の範囲など違います。
私は30歳のとき(いまから20年以上前)係長からスタートし部長まで昇進しました。一番多いときに部下は10人いました。部署はカスタマーサービス(営業部サポート含む)でしたので忙しい部署でした。
この記事は、いま女性管理職の方、またこれから女性管理職になる可能性のある方に向けて、
- 女性管理職が疲れると感じるとき
- 疲れる原因に対しての対処方法
- 女性管理職ならではの良さ、メリット
について解説します。この記事を読んでいただければ、少し前向きに気持ちの切り替えをできるかもしれません。1人で頑張りすぎないようにぜひ参考にしてください。
疲れたと感じたとき

自分の上司が疲れた顔で仕事をしていると、部下は言わないだけで心配してます。
管理職は疲れていても顔に出さない、口にださないように気をつけなければなりません。しかし管理職であっても1人の人間です。わたしが疲れを感じた5つの状況はこちらです。
 いつき
いつき疲れると余裕がなくなり負のスパイラルにハマることが何度もありました。
やることが多くて残業が多い
プレイイングマネージャーでしたので、自分の業務もこなしながら部下のサポートを行ってました。
役職手当だけで残業手当はありません。土日も仕事をしてました。
責任感の強さは人一倍ありましたので、土日仕事をして自分の部署を批判されたくなかったのです。
しかしその責任感も誰も理解してくれないと感じた時、心身ともに疲れを感じてました。
相談できる相手がいない
管理職の経験がある友人がいなかったので、同じ悩みを共有できなかったのです。
今のようにSNSで女性管理職の情報をありませんでしたし、試行錯誤しながら進めていくしかありませんでした。



他部署の管理職に相談するにしても部下の愚痴は言えません。
部下同士が仲が悪い
カスタマーサービスの女性は、顧客、営業から色々なことを依頼されますので、苦情を受けたときはかなりダメージがあります。
同僚同士で愚痴とか言い合って励ましあってほしいですが、犬猿の仲の同僚がいると職場の雰囲気は最悪です。
社会人になっても大人げない人はいます。仲が悪い場合、席を端と端で離す、周りに影響があるときは他部署へ異動も人事部にお願いしてもらったこともあります。
「業務量をこなす」体の負担より、「人間関係のこじれ」に対する精神的な負担のほうが疲れのダメージは大きかったです。
上司と部下の板挟み


一つ例を挙げますと、管理部門(売上目標がない部門)の場合、「コスト削減」が大きな目標になります。
目標達成のために「残業時間削減」をTargetにしますが、「残業削減」は経営層と部下からの板挟みは常にありました。
カスタマーサービスは基本的に顧客や営業から仕事を依頼されます。依頼する側が自分達でやればいいと突き放すと別な軋轢がうまれます。
また経営層は「業務効率化を図って残業時間削減」簡単に言いますが、人を増やさない限り不可能でした。結果的に残業につながる理由をきちんと説明し、現状維持することが精一杯でした。
個人面談・人事考課
個人面談は半年に1回、人事考課は年に1回あり、1対1で面談します。
上司から良いところ、悪いところ、そして改善してほしい点を説明します。相手が納得すればよいですが、不満があるときはやりがいを損なわないよう傷つかないように気も遣います。
人事考課は昇給につながります。基本的に部下全員の平均点をつくり、それより成果があるか、ないかで評価をつけますが、自己評価が高い人を説得するのが本当に大変でした。ドッと疲れたのを覚えています。



年に1回の人事考課は部下にとっては大事なことです。できる限り褒めてましたね。
疲れる原因に対して対処方法
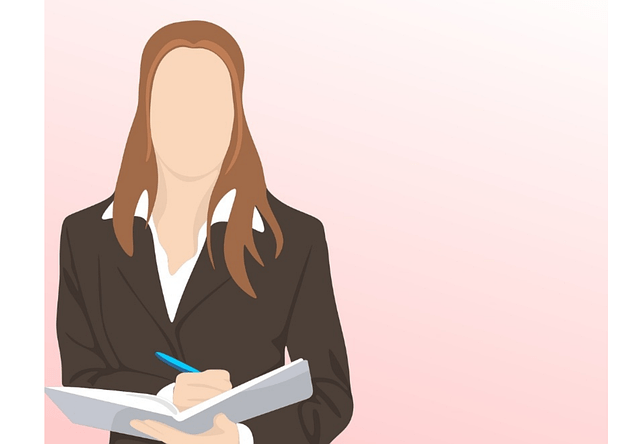
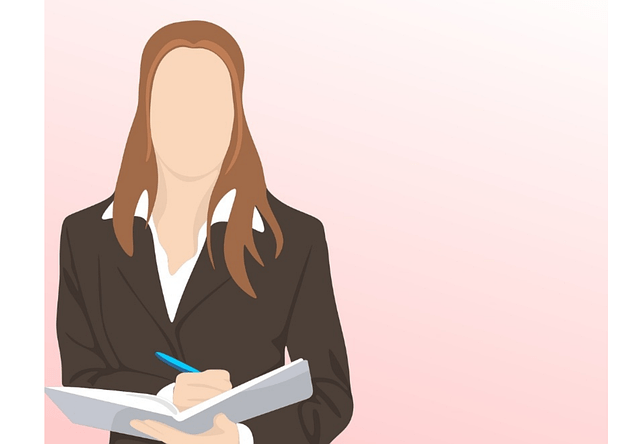
自分のことを、責任感が強く抱え込むタイプだと認識してましたが、かといって自分が何も言わなければ誰も理解してくれません。常に自分で決断していくことが必要です。
しかし管理職に慣れたころ、すべてを真に受けてしまうと体がもたないと気づきました。
自分が気にしているほど、部下は真剣に気に留めてないこともあり、「少しほっておく」という技を覚えたのです。



すぐに動くのではなく1週間ばかり様子を見るとその間に解決していることがありました
その考えに「ゆとり」がでて、1つ1つのことに丁寧に対応することができました。それからは下記の3つのことを意識して実践しました。
部下からよく思われたいと思わない
部下からは嫌われるより好かれたほうが、仕事がやりやすくなるわけではありません。
みなそれぞれ何を考えているかわかりません。全員からの理解を得ようと思うほうが奇跡です。
部門長として「やるべきこと」「守ること」ことはしっかり伝え、部下の機嫌は考えないようにします。
頭に浮かんだら他の話題に切り替えるのがポイントです。
慣れが必要ですが、負の考えが浮かんだら「今日の夜は何を食べようかな?」と別なことを考えることです。前向きな気持ちのままでいられます。
完璧主義をなくす
誰のための完璧主義なのか?考えたほうがいいです。
わたしは自分が満足するために細かいところまで一人で抱え込んでやってました。しかし誰もその資料をみない、必要とされなかったら、傷つくのは自分です。
迷惑かけない程度にほどほどに対応することが重要です。状況によって必要になればさらに対応すればよいです。
最初から完璧にやろうとすると疲れますので「必要になったらやろう」という気持ちのほうが楽です。



前もっての準備は大事ですが、無理しない程度でほどほどにします
上司をうまく巻き込む
なんでも自分でやろう、やろう!と思うと疲れてしまいます。
自分の力では対応できないことが発生したとき、上司に相談し、問題解決するためにうまく巻き込むことが重要です。案外上司は部下から相談されるとうれしいものです。
早いうちから上司に相談し助言に従ってActionし、それに対してフィードバックすることで上司との信頼関係もできますし、問題がすぐに片付くこともあります。自分のチームが良い方向へいけば一石二鳥です。
こちらの記事も参考にしてください。
女性管理職ならでの良さ、メリット5つ


管理職に昇進するには、上司から「管理職にならないか?」と事前の打診があるはずです。その際どのような理由で推薦しているのか伝えるはずです。
昇進ですので、あなたのことを認めているからに違いありません。私自身もリーダーシップを褒められ、悪い気はしなかったので「ダメなら退職しよう」と軽い気持ちで始めました。
管理職になって疲れることのほうが多かったですが、でも良かったなと思うこともありましたので、5つメリットをあげます。
自分の成長につながる
「役職が人を育てる」とある上司に言われました。
責任が大きくなりますので、自分に足りないものは努力して習得しようとします。また部署内の人間関係についても色々学び、たくさんの気づきがあります。
部署全体の最適化を考えるために、視野を広くもつことが必要であり自然とたくさんの努力をしてました。自分の成長は自分ではよく分からないこともありますが、人事考課のときに自分の上司に褒められるとうれしかったです。
給料が上がる
基本給のベースが上がるのと、役職手当がつきますので、年収ですと100万円ぐらい違った年もありました。
また部門目標に達成するとインセンティブもでる会社でしたので、管理職ですとさらに手当は多かったです
土日も仕事をしてましたのでどちらがメリットがあるのか分からない時期もありましたが、お給料が上がるのは素直にうれしかったです。
自分の裁量で決められることが増える


自分の価値観で判断できることは、責任も伴いますが、やりがいにつながります。
自分は「正しくない」と思っても上司の指示に従わないいけないとき、やはりストレスが溜まります。
時には間違った判断をして失敗しますが、その対応を責任もって行うことで自分への成長につながり満足した仕事ができます。
会社の重要な情報を知る
管理職になると、一般職ではアクセスできないフォルダにアクセスできたり、社長から管理職にしか伝えられない情報を共有されたときは、優越感を感じたりしました。
その特別感がやりがいにつながります。
部下の成長にやりがいを感じる
色々な部下がいましたが、人事考課や個人面談なので色々話し合い改善したほうがよい点を指摘し、素直に対応する部下ほど成長が早いです。
何年か後にその部下が管理職になりリーダーシップを発揮しているのをみると嬉しい気持ちになりました。
女性管理職は人材育成が大きな仕事


女性管理職に向いている人は、ズバリ、、、
だと思います。責任感の強さ、柔軟な対応力、論理的な思考ができる人なども挙げられますが、でも一番大事なことは次の世代を育てられる人は最強です。
もちろん管理職になりたてのころは十分な育成を受ける必要があります。
部下の育成や部門内の目標達成のためにやることがたくさんあって、管理職になりたがらない気持ちもよくわかります。
でも管理職の楽しさは人間関係から生じると思います人とのコミュニケーションをとるのが好きな方は管理職に挑戦していただきたいです。